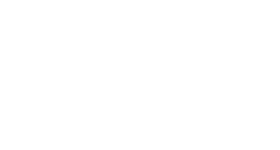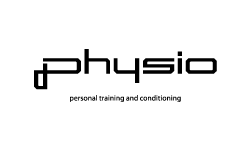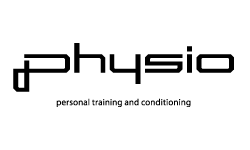Conditioning for the future.
未来に向けたコンディショニングを。

より良い未来を迎えるには
未来に向けたコンディショニングが必要だ。
より健康な明日のために。

①QOLの改善
一般に、ADLが低くなるとQOLが低下するが、ADLの低下は必ずしもQOLの低下を引き起こすわけではない。恒久的な疾患によりADLが低下した人でも、生きがいを見つけて高いQOLを維持している人がいる。我々はQOLを考えてプログラムを処方しなければならない。
大事なことはいかにその人の生活の質を豊かにするか。裏を返せば、なにがその人の生活の質を低下させているかを初期評価で知らなければならない。
- 疾患の改善⇒抱えている疾患そのものの改善
- 疾患に関わる問題・不安の改善⇒日常生活に踏み込んだ評価・治療計画
- 不定愁訴の改善⇒違和感や不安感、客観性はないが主観的には非常に重要
②疾患の改善
- 解剖学的要素疾患に繋がる、または疾患によって引き起こされた解剖学的な異常
例:膝OAにおける内反膝、インピンジメントによる棘下筋萎縮、RAにおける関節拘縮など
- 運動学的要素疾患に繋がる、または疾患によって引き起こされた運動学的な異常
例:ミクリッツ線変位におけるストレス増大、肩関節外転90°での回旋不足など
- 生理学的要素疾患に繋がる、または疾患によって引き起こされた生理学的な異常
例:糖尿病における毛細血管の弱化、メタボリックシンドロームにおけるレプチン抵抗性など
- 医学的要素疾患に繋がる、または疾患によって引き起こされた医学的な異常
例:腎不全における高血糖、腎不全におけるメタボ、膝OAにおける半月板損傷など
- 心理的要素疾患に繋がる、または疾患によって引き起こされた心理的な異常
例:椎間板ヘルニアにおける躁うつ、メタボリックシンドロームにおける過食など
③より良いコンディショニングへの戦略的トレーニング
基本動作やスポーツにおけるパフォーマンスの改善を目指す運動器の運動療法において、評価とは対象者の動作能力の低下を引き起こす機能障害を見つけ出し、適切な治療プログラムを作成するための情報を抽出するプロセスである。
評価をせずに運動療法に取り組むことは、地図を持たずに旅に出るようなもので、目的もそこで何をするのかも不明確な状態となる。
①力学的ストレスの明確化 ②解剖学的機能評価 ③運動学的機能評価
フィジオの提供するもの

①徒手によるコンディショニング⇒いわゆるマッサージ、ストレッチなどが中心。
②物理療法によるコンディショニング⇒超音波、電気、その他温熱や物理刺激など。
③栄養療法⇒分子整合栄養学、サプリメントなど補助食品
④運動療法⇒コレクティブ・エクササイズなど予防医学の側面
⑤睡眠など生活習慣のリカレント教育⇒健康増進という意味合いでの専門的な情報提供・情報発信
これらすべてはお客様のQOLを豊かにするものであるべきであり、フィジオのコンディショニングはこれらを実現するためのサポートを行っています。